|
今年度より、蔵王町新学力調査が
小中学校共にスタートしました! |

小学3年生算数の授業「3・4位数のたし算とひき算」(円田小)
町教育委員会では、蔵王町の小中学生の学力の実態を把握するため、平成14年度から、平成25年度まで12回、小・中学校の標準学力調査(小4・小6・中2)を実施してきました。
今年度からは子どもたちの学力の状況をより適切に把握するため、新たな蔵王町学力調査を行いました。
主な変更点は次に挙げる3つです。
①調査対象の枠を広げ小2から中2までとしたこと。
②マークシート方式(全ての解答が選択式のもの)から思考力・表現力が分析できる記述式に変更したこと。
③これまで2月に実施し、年度をまたいで考察してきたことを、4月に実施し、その結果を年度内に活用できるようにしたこと。
このことにより、蔵王町の小中学生の学力を幅広く把握することができます。そして、今後の学力向上の方向性がより明確になると考えています。
また、平成26年度も家庭での様子を知るために、小学5・6年生、中学3年生を対象に、「生活アンケート」を行い、「起床時刻」「就寝時刻」「睡眠時間」「家庭学習時間」「テレビ視聴時間」「ゲーム・インターネット・携帯メール時間」の調査結果をまとめました。こちらの方は昨年度までの調査と同様で、変更点はありません。
小学校の現状と課題
今回記述式の調査に変更したことにより、昨年度までの結果と単純に比べることはできません。今後各学校でこの結果を分析し、学力向上に向けた取組を更に進めてまいります。
実施した「国語」「算数」の結果を分析したものをご報告します。
国語
町全体の平均正答率を学年別に見ると、5・6年生が全国平均との開きがやや大きいことが分かりました。
国語の「基礎となる力」と「活用する力」の2つの視点で分析したところ、「活用する力」に、より課題が見られました。ここでの「活用する力」とは、言葉や文章から、相手が伝えたいことを考え判断したり、自分が伝えたいことを表現したりする力のことを示します。「基礎となる力」では、学年が上がるごとに課題がはっきりしてくることが分かりました。
国語は、すべての学習の基礎となる教科です。各学校では、引き続き授業の工夫や言語活動の充実、読書の推進に取り組んでいきます。その中でも、自分の考えや思いを相手に分かりやすく伝える力を身に付けられるように工夫していきます。また、学んだことを他教科や日常生活に生かせたという実感が持てるように努めていきます。
|
家庭でもできる4つの取組 |
蔵王町では、昨年度より各学校に学校図書館支援員を配置し、読書環境を整え、本に親しみ、たくさん本を読む子どもを育てたいと考えています。町立図書館も充実しておりますので、有効にご活用ください。
算数
平均正答率を見ると、全ての学年で全国平均をやや下回る結果となりました。特に「日常生活の中で必要とされる筋道を立てて考えたり、表現したりする力」が弱いことが分かりました。いわゆる「活用力」です。さらには、「算数への関心・意欲・態度」が低いことも明らかになりました。
各学校では、これまでにも学力向上に向けて特色ある取組を試みてきましたが、今回の結果を受けてより効果的な指導を推進できるように努めていきます。その中でも、日常での活用場面を重点的に取り上げることで、課題である「生活とのつながり」や「算数で学んだことを役立てていく力」を高めていくことができると考えています。
「積み重ねの教科」とも言われる算数です。家庭では今日学習した内容を毎日復習することで基礎力の定着を図ることが大切です。
また、普段の日常生活の中で、算数で学習したことを生かせる場面もたくさんあります。このような機会にお子さんと一緒に算数的な課題を考えていただくこともお子さんの学習意欲につながります。
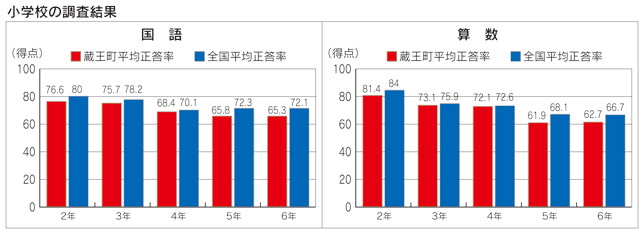
町立小学校5校の学力向上への取組
|
小学校共通
|
|
●朝の時間を利用したドリルや読書の実施 |
|
円田小学校
|
|
●教員の教科指導力向上[校内研究(言語活動の充実)、模擬授業・研究授業の実施、現職研修の充実] |
|
平沢小学校 |
|
●教員の教科指導力向上[国語科の校内研究、模擬授業やワークショップ型の事後検討会、学力向上サポートプログラム事業研修会など] |
|
永野小学校 |
|
●教員の教科指導力向上[校内研究(算数科)における事前・事後検討会や模擬授業等] |
|
宮小学校 |
|
●教員の教科指導力向上[校内研究(算数)、ワークショップ型の事後検討会、少人数指導(算数)] |
|
遠刈田小学校 |
|
●教員の教科指導力向上[国語科を中心とした校内研究の推進、週一回打合せでの生徒指導上の情報交換、学力向上サポートプログラムの活用] |

中学1年生社会の授業「聖徳太子の政治改革」(円田中)
中学校の現状と課題
町内3校の1・2年生を対象に、今年4月に実施した学力調査の結果は、グラフに示した通りです。今回の学力調査は、各教科の基礎、活用(※1)がどの程度身に付いているかをみる問題です。問題は、1年生は小学校、2年生は中学1年生の内容です。
1年生4教科、2年生5教科の合計点数は、基礎、活用ともに全国平均を下回っていることが分かりました。教科別では、1年理科の活用と2年社会の基礎、活用が全国平均を上回りました。
今回の学力調査を受けて、今後重点的に指導すべき内容は、下の表の通りです。
「確かな学力を育む」ことは、一朝一夕にできるものではありません。しかし、3校とも、生徒が、課題をしっかり考え、考えを自分の言葉等で表現できる学習活動に力を入れています。これは、学力を育成する上で大きな柱のひとつであり、現在全国的にその充実が叫ばれている「知識を活用し課題を解決する力」につながります。また、家庭学習の充実も学力を育む上で不可欠です。その内容や方法、学習量等について適切な指導を継続して行っていきます。
※1:様々な実生活の場面や課題を解決するために知識や経験を生かして自分の考えをまとめ、行うこと
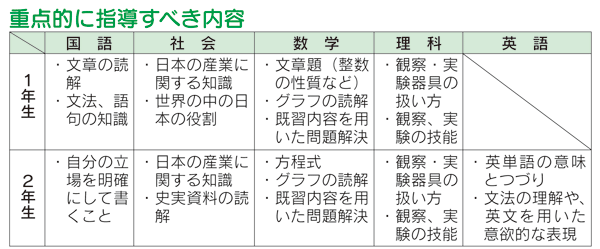
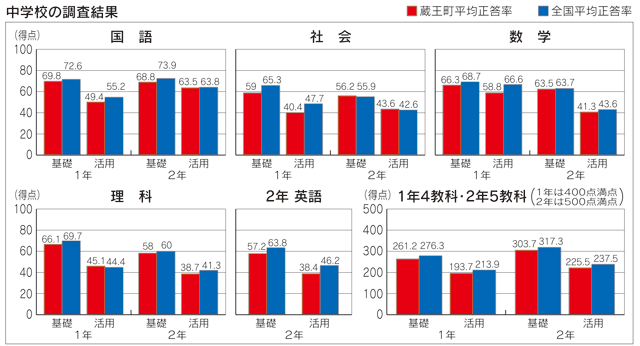
町立中学校3校の学力向上の取組
|
中学校共通
|
|
●毎日の「朝の読書」の実施 |
|
遠刈田中学校
|
|
●話合い活動を充実させた授業づくりの推進(校内一斉研修会を年2回実施) |
|
円田中学校 |
|
●学ぶ力を高めるための授業づくりの推進 |
|
宮 中 学 校 |
|
●論理的な思考を高めさせるため、話の聞き方、発表の仕方等の継続指導 |
|
家庭でもできること
|
生活アンケートから
生活アンケートによると、昨年度までとは傾向が変わってきたことが読み取れました。
小学生の「睡眠時間」は8時間くらいで、昨年度までと変化はありませんが、起床・就寝時刻を見てみると、早寝・早起きの傾向になっています。これは、学校や家庭での「早寝・早起き・朝ごはん」の声がけが習慣化されてきたことの表れだと考えられます。
ただ、「学習時間」と「テレビ・ゲーム・インターネット・携帯メール時間」の関係を見ると、「学習時間」では30分~1時間の児童が15%程度増え、1時間~1時間半の児童が15%程度減っています。つまり「学習時間」が30分程減っていると考えられます。
その分、「テレビ視聴時間」で4時間くらい、「ゲーム・インターネット・携帯メール時間」でも2時間以上の児童がそれぞれ10%程度増えており、「テレビ・ゲーム・インターネット・携帯メール時間」の増加が「学習時間」の減少につながっていると考えられます。
中学生は、就寝・起床時刻が遅くなっている傾向が見られました。12時以降に就寝し、7時以降に起床する生徒が、昨年度より大幅に増えています。睡眠時間では、7時間の生徒が10%程度減り、その分6時間の生徒が10%程度増えています。これは睡眠時間が減少傾向にあることを示しています。
「学習時間」では、1時間~3時間学習する生徒が減少し、1時間未満の生徒が大幅に増えています。このことは、「ゲーム・インターネット・携帯メール時間」が、2時間以上の生徒が10%程度増えていることによると考えられます。
小学校・中学校ともに「ゲーム・インターネット・携帯メール時間」が増えてきているのは、大変気がかりな点です。睡眠時間を削ってまでも、テレビやゲーム機器・スマートフォン等に向かっている子どもたちの姿が見えてきます。
また、宮城県全体でも小学生は長時間テレビを見たりゲームをしたりする割合が、全国値よりも高いという結果も出ています。睡眠時間の確保は、健全な頭脳形成には不可欠なことと言われています。その弊害が出てくる前に、皆でもう一度睡眠の大切さを一緒に考えていきたいものです。また、自己の教養を高めるための家庭学習や読書の時間、家族での語らいの時間等の必要性を、様々な機会を利用して語りかけていきましょう。
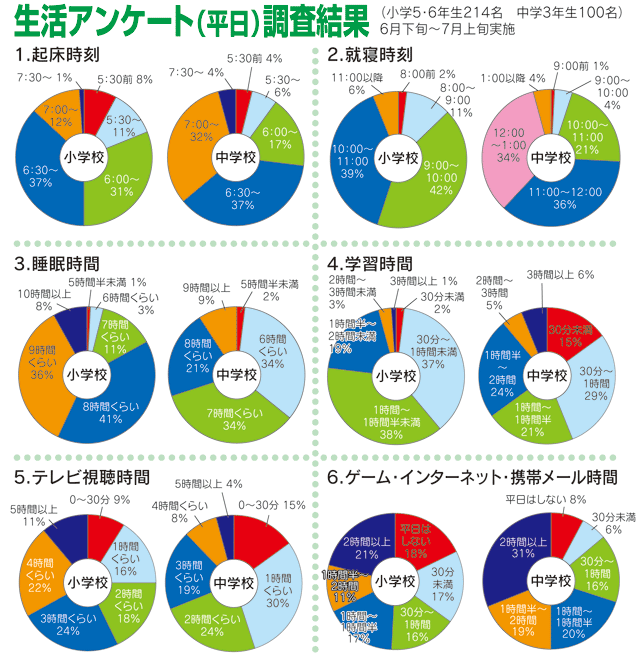
問い合わせ先/各小中学校または、町教育委員会教育総務課 TEL0224-33-3008