|
平成24・25年度
後期高齢者医療保険料が変わります |
75歳以上対象
| 平成24年度・25年度の後期高齢者医療保険料について |
保険料は、被保険者が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて決まる「所得割額」の合計額となり、県の後期高齢者医療広域連合で2年ごとに決められます。
なお、新しい保険料への移行は8月となりますので、平成24年度の保険料額は7月にお知らせいたします。
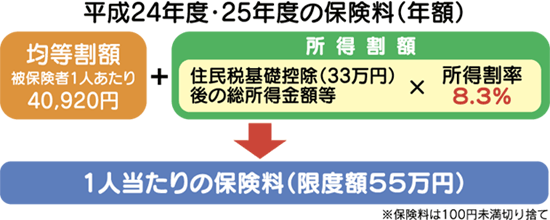
※均等割額、所得割率は、宮城県内で均一となり、2年ごとに見直されます。
※保険料限度額は年額55万円となります。
※遺族年金や障害年金については、保険料を計算する際の所得の合計に含みません。
※年度の途中で加入された方は、加入された月から月割計算となります。
| 所得の低い方に対する軽減措置について |
所得の低い方は、下記のとおり、世帯(被保険者全員と世帯主)の前年中の所得に応じて、均等割額(年額40,920円)が軽減されます。
|
軽減割合
|
世帯(被保険者および世帯主)総所得金額等
|
軽減後の均等 |
|
9割 |
基礎控除額(33万円)を超えない世帯で、 「被保険者全員が年金収入80万円以下」の世帯(その他各種所得がない場合) |
4,092円
|
|
8.5割 (注1) |
基礎控除額(33万円)を超えない世帯 |
6,138円
|
|
5割 |
基礎控除額(33万円)+24.5万円×世帯に属する被保険者数(世帯主である被保険者を除く)を超えない世帯 |
20,460円
|
|
2割 |
基礎控除額(33万円)+35万円×世帯に属する被保険者数を超えない世帯 |
32,736円
|
※注1 本来は7割軽減ですが、平成24年度は8.5割軽減となります。
※65歳以上の公的年金受給者は軽減判定において、年金所得から15万円が控除されます。
※軽減判定は4月1日(4月2日以降新たに加入した場合は加入した日)の世帯の状況で行います。
※世帯主が後期高齢者医療制度の被保険者でない場合にも、その世帯主の所得は軽減判定の対象になります。
|
後期高齢者医療保険証・
国保高齢受給者証の更新 |
◆被保険者証(保険証)
75歳以上の方が加入している後期高齢者医療制度の保険証は、7月31日をもって有効期限を迎えます。新しい保険証は7月下旬に郵送いたします。
また、更新に伴い、保険証の色がこれまでのオレンジ色からみどり色に変わります。(昨年の収入状況により、一部負担金割合(1割・3割)が変更になる場合もあります)8月から医療機関などで受診するときは、みどり色の保険証を忘れずに提示してください。
なお、現在使用している保険証(オレンジ色)は8月1日以降に町民税務課、各出張所に返却願います。特別な理由がなく保険料を滞納されたままの方については、通常の保険証よりも有効期限が短い保険証が交付されます。保険料は納期内に納めましょう。
問い合わせ先/町民税務課 TEL0224−33−3001
県後期高齢者医療広域連合 TEL022−266−1021
◆国保高齢受給者証
高齢受給者証(70歳から74歳の方)は7月31日をもって有効期限を迎えます。新しい受給者証は後期高齢者医療制度と同じく、一部負担金の変更などがあり、7月下旬に郵送いたします。8月からは新しい受給者証を利用してください。
なお、現在使用している受給者証は8月1日以降に町民税務課、各出張所で返却願います。
医療機関などへ受診するときは、高齢受給者証と国民健康保険の保険証を忘れずに提示してください。
問い合わせ先/町民税務課 TEL0224−33−3001
|
病院等で医療費がたくさんかかりそうなときは
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請を |
入院(通院)するときは、医療機関などで1カ月(1日から末日)に支払う保険診療の自己負担額が一定以上の高額となるとき「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、認定証)を医療機関の窓口に保険証と一緒に提示することにより、自己負担額や食事負担額が軽減されます。
現在、認定証の交付を受けている方で、引き続き交付を希望する方、または、新たに認定証の交付を希望する方は申請してください。
申請できる方
○住民税非課税世帯の方で、後期高齢者医療制度に加入している方または国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方。
○70歳未満の国民健康保険加入者は、必要に応じて交付できます。
※ 住民税未申告世帯または、国民健康保険税に未納のある世帯については、認定証は交付されません。
申請に必要なもの/後期高齢者医療被保険者証または国民健康保険の被保険者証・印鑑
申請・問い合わせ先/町民税務課 保険係 TEL0224−33−3001
|
介護保険負担限度額認定証の
更新手続きのお知らせ |
介護保険では、特別養護老人ホームや老人保健施設などに長期入所または、ショートステイを利用している低所得の方を対象に、居住費(滞在費)と食費が利用者負担段階に応じて軽減される制度があります。
現在認定証をお持ちの方は、有効期限が6月30日となっておりますので、更新の必要な方は手続きをしてください。また、新規申請の方については、随時受け付けております。
対象となる方の要件
|
利用者負担段階 |
対 象 と な る 方 |
|
第1段階 |
老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税の方、生活保護の受給者 |
|
第2段階 |
世帯全員が市町村民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
|
第3段階 |
世帯全員が市町村民税非課税で第2段階に該当しない方 |
申請期間/7月2日(月)から31日(火)まで下記へ
申請に必要なもの/負担限度額認定申請書、保険者証
申請・問い合わせ先/町保健福祉課 TEL0224−33−2003